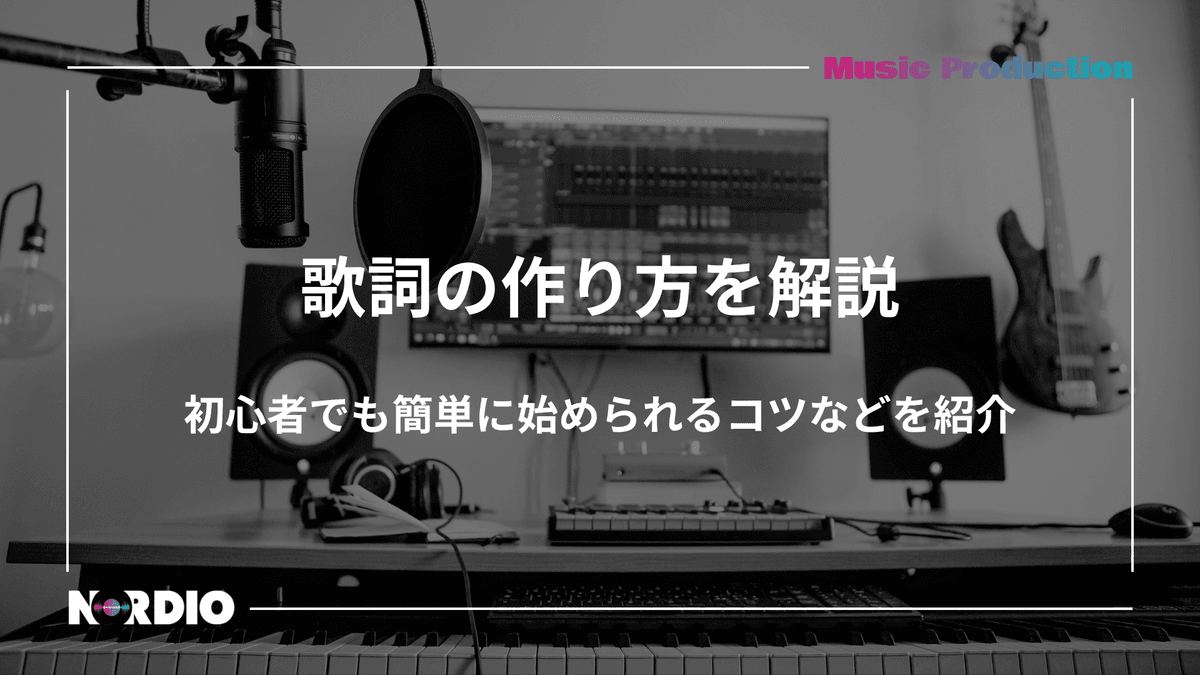今回の記事では、初心者でも簡単に作詞を始める方法を解説します。作詞は詩を書くこととは似て非なるものであり、自由さと音楽との兼ね合いのバランスが難しいものです。それでも、以下の内容を抑え、試行錯誤を重ねれば、どんどん表現力も向上していくでしょう。この記事が作詞活動の第一歩を支えるものになれば幸いです。
歌詞とは?
歌詞とは、ご存知の通り、メロディーに合わせて歌われることを前提とした作られた言葉です。音楽全体で伝えたいメッセージを言葉としてダイレクトに表現する、音楽において非常に重要な要素です。
▼こちらの記事では、音楽制作全般について解説しております。ぜひご覧ください。
https://nordio.jp/making/music_production_all-cover
歌詞は詩とは違う
歌詞と詩は似ているようで、実は大きな違いがあります。詩は基本的に朗読したり、目で読んだりすることを前提としていますが、歌詞はメロディーやリズムに乗せて歌うことを前提としています。そのため、詩に比べて言葉のリズムや響き、そして「歌いやすさ」が非常に重要になります。歌詞を書くときは、単に言葉を並べるだけでなく、メロディーと一緒にどう聞こえるかを意識することが大切です。
歌詞の大まかな構成
歌詞の構成は、曲全体をどう見せるかに関わる大切な要素です。一般的な構成には「Aメロ」「Bメロ」「サビ」「Cメロ」「Dメロ」「間奏」「アウトロ」などがあります。中でもAメロは導入部分、サビは曲の中で最も伝えたいメッセージを乗せる部分、Cメロは展開を変えて曲に奥行きを持たせる部分と覚えておくと良いでしょう。これらの構成を意識することで、ストーリー性のある歌詞を作りやすくなります。
作詞のための5ステップ

1. テーマを考える
まずは、曲全体で何を伝えたいのか、中心となるテーマを決めましょう。「失恋」「友情」「夢を追うこと」「日常の風景」など、どんなに小さなことでも構いません。
このテーマが、歌詞の土台となります。漠然とした感情をテーマにしたい場合は、その感情が生まれたきっかけや、その感情から連想される具体的な「モノ」や「場所」を考えてみると、アイデアが広がっていきます。
2. 構成を考える
テーマが決まったら、次に曲の構成を考えます。たとえば「失恋」をテーマにするなら、「Aメロで出会いを描く→Bメロで別れの予感→サビで別れの辛さを爆発させる」といったように、ストーリーを組み立てていきます。
この段階で、歌詞の起承転結を意識すると、より聴き手の心に響く歌詞が書けるようになります。
3. 実際に書いてみる
構成が決まったら、いよいよ実際に言葉を書いてみましょう。最初は完璧を目指す必要はありません。頭に浮かんだ言葉やフレーズを、どんどん書き出してみてください。韻を踏む場所や、言葉の響きを意識しながら書くと、メロディーに乗せたときに心地よい歌詞になります。
4. 表現のブラッシュアップを行う
書き出した言葉を、より魅力的にするために磨きをかけます。ありきたりな表現を、自分だけの言葉に置き換えてみましょう。「悲しい」という感情を「雨が降り続く」と表現するなど、比喩や情景描写を加えてみるのも効果的です。このステップで、歌詞に「あなたらしさ」を加えていきます。
5. 音に合わせてみて、再度ブラッシュアップ
完成した歌詞を、実際にメロディーに合わせて歌ってみましょう。リズムに乗りやすいか、不自然な箇所はないかを確認します。声に出して歌ってみることで、思わぬ発見があるはずです。もし歌いにくいと感じた箇所があれば、言葉を入れ替えたり、リズムを変えたりして調整しましょう。
作詞のコツ
普段から、思いついた単語などをメモしておく
歌詞のアイデアは、日常生活の中に隠されています。ふと目にした風景、心に浮かんだ感情、誰かの言葉など、心に留まった単語やフレーズをスマホのメモ機能やノートに記録する習慣をつけましょう。これらが、いざ作詞をしようとしたときに、あなただけの言葉の引き出しとなってくれます。
まずはサビの歌詞から考える(作詞の順番を考える)
作詞の進め方に決まったルールはありませんが、サビから先に考えるのも一つの有効な方法です。サビには曲の核となるメッセージが詰まっているので、ここを最初に固めることで、AメロやBメロの内容が自然と決まってきます。サビのインパクトを最大化することが、曲全体の魅力を高めることにつながります。
5W1Hを意識する
作詞に行き詰まったら、5W1H(When, Who, Where, What, Why, How)を意識してみましょう。「いつ、誰が、どこで、何を、なぜ、どのように」という視点で考えてみると、歌詞に具体的な情景が生まれてきます。例えば「夕焼けの帰り道で、君と二人、何を話したか」といったように、物語の解像度を高められます。
表現する場面は絞る
一つの歌詞に、たくさんの情報を詰め込みすぎないように注意しましょう。特に初心者の方は、表現したいことが多すぎて、まとまりのない歌詞になってしまうことがあります。一つの曲で一つのシーンや感情に焦点を絞ることで、より深く、聴き手に伝わりやすい歌詞になります。
作詞を行う時のよくあるミスと注意点
よくあるミス | 注意点/防止策 |
|---|---|
歌いやすさが全く意識されていない |
|
言葉を詰め込みすぎる |
|
既存の曲と似過ぎてしまう |
|
歌いやすさが全く意識されていない
どれだけ素晴らしい言葉を並べても、歌いづらい歌詞は聴き手に届きにくくなってしまいます。例えば「あいうえお」が連続する言葉や、早口で言いにくいフレーズは避けるようにしましょう。歌詞は「読む」ものではなく「歌う」ものだということを常に意識することが大切です。
詰め込みすぎる
伝えたいことが多すぎるあまり、言葉を詰め込みすぎてしまうのは避けたいポイントです。文字数が多すぎると、メロディーと合わなくなり、聴き手も内容を理解しにくくなります。シンプルで力強い言葉を選ぶことで、かえってメッセージが心に響くこともあります。
既存の曲と似過ぎてしまう
好きなアーティストの歌詞を参考にすることは大切ですが、似すぎるとオリジナリティが失われてしまいます。参考にするのは、あくまで「表現の仕方」や「テーマの扱い方」に留め、自分だけの言葉で表現する努力をしましょう。
▼既存の曲から歌詞を参考にするTipsはこちらの記事で解説しております。ぜひご覧ください。
作詞に役立つ表現技法
リフレイン
同じ言葉やフレーズを繰り返す技法です。同じ言葉を何度も使うことで、聴き手に強い印象を与え、伝えたいメッセージを強調できます。また、メロディーと合わせて使うことで、リズム感を生み出す効果もあります。
倒置法
「〜が、好き」というところを「好きだ、〜が」のように、通常の語順を入れ替える技法です。意外性のある表現で聴き手の注意を引きつけ、より感情を込めた印象的な歌詞になります。
比喩表現
あるものを、別のものに例える技法です。「君の笑顔は太陽みたいだ」といったように、抽象的な感情や情景を、具体的なイメージで表現できます。比喩を使うことで、聴き手の想像力をかき立て、歌詞の世界観を豊かにできます。
作詞に役立つアプリ3選
作詞に行き詰まった時や、思いついたアイデアをすぐに形にしたい時に役立つアプリはたくさんあります。これらのツールを使うことで、隙間時間を活用して効率的に作詞を進めることができます。例えば、メモ機能に特化したシンプルなアプリから、韻を踏む言葉を探してくれる便利なアプリまで、自分に合ったものを見つけてみましょう。
作詞ノート

作詞ノートは、株式会社LUMITECが提供する、作詞活動をサポートするiOS/Android対応のアプリです。思いついた歌詞のフレーズやアイデアを簡単に記録することができます。また、メロディーに合わせたコードをメモすることも可能で、作詞と作曲のアイデアを一つの場所で管理できます。ジャンルやテーマごとにメモを整理したり、キーワードで検索したりする機能も備えているので、歌詞の遂行や構成を考えるのにも役立ちます。
Lyrics Notepad

Lyrics Notepadは、詩人やソングライターのためのオールインワン創作ツールです。内蔵レコーダーでメロディを録音したり、韻を踏むための色分け機能やシラブルカウンターでリズムを整えたりと、多彩な機能を備えています。
また、言葉に詰まった時は類義語や定義を調べられる機能もついています。アイデアを整理できるノートとしても活用できるため、あなたの創作活動を強力にサポートしてくれるでしょう。
RhymePlus!

RhymePlus!は、韻を踏む語句を検索できる無料のアプリです。韻を踏みたい単語を入れて、検索したい文字数や語頭、語尾から検索するかの条件を指定して、検索を行います。
また、ここで検索した語句をお気に入りに追加することで、いつでも見返せるようにストックすることができます。歌詞の言葉をブラッシュアップする段階で、韻を踏む言葉を検討してみるのも1つの手でしょう。
作詞でAIを役立てる方法
近年、作詞におけるAIの技術も目覚ましく発展しています。自分の発想が行き詰まったときに活用するのもいいですし、あるいは、まずAIに大まかに歌詞を生成してもらいその言葉を自分でブラッシュアップしていく方法もあるかもしれません。
大切なのは、自分が伝えたいことを綺麗に伝えられるか、です。自分のスタイルに合わせて、ツールとして上手に使いこなしましょう。
作詞を手伝ってくれるAIツール
特定のキーワードやテーマを入力するだけで、自動的に歌詞を生成してくれるツールがあります。これらのツールでアイデアのヒントを得たり、行き詰まった時の突破口として活用してみるのも良いかもしれません。
以下、いくつかAI作詞ツールを紹介します。
Mureka

Murekaは、中国のテック企業によって作られたAI音楽生成サービスです。曲名を入力するだけで1曲分の歌詞を生成してくれます。今回は「夏の終わり」と入力してみました。これを入力するだけで、VerseやChorusなど構成を整理しながら、1曲分すべての歌詞を生成してくれます。あくまで作詞の補助に使いたい場合は、1曲分まるっと作詞してもらったものを見ながら、作詞の方向性を検討する、のような使い方がいいかもしれません。
Shikaki

Shikakiは自分の作詞アイデアとAIの補助を同時に含むことが出来る作詞補助ツールです。AメロやBメロなどのセクションごとに音数を指定して歌詞の生成を行ってくれ、行ごとに歌詞の再生成が可能です。
AIが生成した歌詞を、その場で自分の手で修正することも可能です。AIの力を借りつつ、自分のアイデアをその場で反映し作詞することができます。
TopMedi

TopMediは完全無料で使用できるAI作詞ツールです。「曲名」と「曲の説明」を入力するだけで歌詞を生成してくれます。特に「曲の説明」では、自分が構想している情景や感情を具体的に記述することで、よりイメージに近い歌詞を生成してくれるようになります。
また、この構想が具体的に記述できなくても、「ランダム説明を生成」を押すと、曲名に応じて説明を生成してくれるので、これを起点に構想を膨らませるのも良いかもしれません。
まとめ
この記事では、作詞を始めたい初心者の方に向けて、基本的なステップやコツ、注意点を紹介しました。作詞は、あなたの内にある感情や考えを形にする素晴らしい表現方法です。難しく考えすぎず、まずはメモをとる習慣をつけ、楽しみながら言葉を紡いでみてください。あなただけのオリジナルな歌詞が生まれることを応援しています。