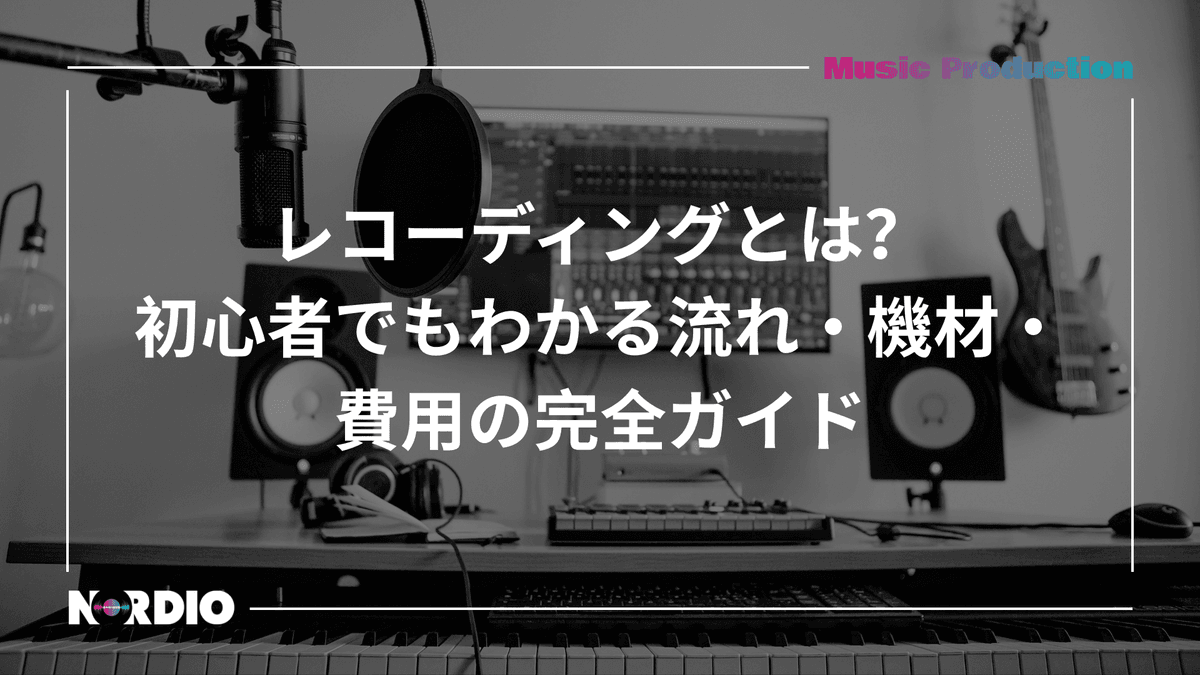「レコーディングって何から始めればいいの?」「機材や費用はどのくらい?」
初めて録音に挑戦しようと思ったとき、そんな疑問や不安を感じる方は多いのではないでしょうか。
レコーディングは、ただ音を録るだけではなく、音楽や声を“作品”として仕上げる大切なプロセスです。しかし、専門用語や機材の種類、スタジオと宅録の違いなど、初心者にはわかりづらい点もたくさんあります。
この記事では、「レコーディングとは何か?」を初心者向けにやさしく解説します。録音の基本的な流れ、必要な機材、費用感の違い、スタジオ録音と宅録(自宅録音)の違いやメリット・デメリットなどを、丁寧にご紹介します。
レコーディングとは?基本の意味と目的

「レコーディング」とは何をすること?
レコーディングとは、演奏や歌声などの音をマイクを通して録音し、音源として残す作業のことです。また、音楽を“作品”として形に残すための重要な工程です。 なぜなら、演奏や歌を録音し、編集・ミキシング・マスタリングといった加工を施すことで、音楽は初めて配信や販売に適した状態になるからです。
たとえば、あなたが普段聴いているCDや配信曲も、すべてこの工程を経ています。つまり、アーティストが自分の音楽を“作品”として完成させるために欠かせない工程といえるでしょう。
どんな人がレコーディングするのか
レコーディングは、プロのミュージシャンやレコード会社所属のアーティストだけのもの…と思われがちですが、実際にはアマチュアやインディーズのアーティスト、趣味で音楽制作をしている人たちにも広く活用されています。
例えば…
- インディーズバンドが、自分たちの楽曲を音源として残すため
- シンガーソングライターが、オリジナル曲をYouTubeや配信サービスにアップするため
- ボカロPやトラックメイカーが、仮歌やパートを録音してデモを制作するため
最近では、録音環境の選択肢が広がったことにより、自宅で手軽に録音を始める人も増えてきました。TikTokやYouTubeなどのSNSを通じて音楽活動を始めた若い世代が、パソコンやスマホを使って音作りに挑戦する例も珍しくありません。
さらに、ライブでは伝えきれない細部のこだわりや世界観を、音源としてじっくり表現できるのが、レコーディングの大きな魅力です。
宅録とスタジオ録音の違い
.png?w=360&fm=webp&q=70)
音楽を録音する方法は、大きく分けて「スタジオ録音」と「宅録(自宅録音)」の2つがあります。 どちらも音楽を形にする大切な手段ですが、特徴や使いどころは大きく異なります。
「スタジオってどんなところ?」「自宅で録音しても大丈夫?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。 それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説し、あなたにピッタリの録音スタイルが見つかるようにお手伝いします。
【特徴】 | スタジオ録音 | 宅録(自宅録音) |
|---|---|---|
機材 | 高品質なプロ機材 | 自宅用の手頃なセット |
サポート | エンジニアが担当 | 自分で編集・管理 |
自由度 | 時間制限あり | 好きな時間に自由に録音 |
コスト | 数万円 / 曲~ | 初期費用のみで低コスト |
スタジオ録音と宅録は、それぞれにメリット・デメリットがあり、向いている人も異なります。自分の目的や制作スタイルに合わせて選ぶことが大切です。以下に、それぞれの特徴をわかりやすく整理しました。
スタジオ録音が向いている人
- 高音質でプロの仕様の音源を作りたい
- 経験豊富なエンジニアに録音・ミックスを任せたい
- 自分は演奏や歌唱に集中したい
- 完成度が高い作品を短期間で仕上げたい
宅録が向いている人
- コストを抑えて録音・制作をしたい
- 自宅で自分のペースで作業を進めたい
- 気軽に録音や試行錯誤を繰り返したい
- 機材やソフトを自分で選び、スキルを身につけたい
どちらが優れているという話ではなく、大切なのは「自分の目的やスタイルに合っているかどうか」。たとえば、まずは宅録で試してみて、必要に応じてスタジオ録音にステップアップするという選択肢もあります。
これから録音にチャレンジする人は、無理に完璧を目指さず、自分にとって心地よいスタイルを見つけることが何より大切です。
レコーディングの流れを5ステップで理解しよう

初めてのレコーディングでは、どんな手順で進むのか想像しにくいかもしれません。ここでは、音源が完成するまでの一般的な流れを、5つのステップに分けてわかりやすく解説します。
それぞれの工程で何をするのかをあらかじめ知っておくことで、当日も安心して臨めます。
- プリプロダクション(事前準備)
- セッティング(機材・音作り)
- 録音(レコーディング)
- 編集・補正(ピッチ補正・パンチイン)
- マスタリング(最終仕上げ)
Step 1:プリプロダクション(録音前の準備段階)
レコーディングは、いきなり本番を録るわけではありません。まず行うのが「プリプロダクション(通称:プリプロ)」という準備のステップです。
プリプロとは、本番前に仮の音源を録ったり、アレンジや構成を整えたりする作業のこと。簡単に言えば「録音のリハーサル」であり、ここで作品の土台をしっかり作ります。
プリプロダクションで意識したいポイント:
- 仮歌や仮演奏を録音して、メロディや構成を確認
- テンポ・キー・アレンジを最終調整
- 録音の順番や段取りもここで決めておく
この段階で方向性を明確にしておくことで、本番の録音がスムーズに進み、無駄な録り直しを減らすことができます。
Step 2:セッティング(機材・音作り)
セッティングは、良質な録音を実現するための“環境づくり”のステップです。
この工程では、録音機材の配置や接続、音の作り込みなどを行います。
たとえばマイクの位置や種類を調整したり、エフェクターで音色を整えたりします。この準備次第で、録音クオリティは大きく変わるのです。
セッティングで意識したいポイント:
- マイクの種類や位置を調整し、ベストな音を収録できるようにする
- エフェクターやアンプなどをつなぎ、希望する音色に近づける
- モニター環境(ヘッドホンのバランス)を整える
特にスタジオ録音では、録音エンジニアがここで大きな役割を果たします。 一方、宅録では自分でセッティングを行うことになるため、基本的な知識があると安心です。
このセッティングがうまくいくと、本番での録音のクオリティがぐっと高まります。
Step 3:録音(レコーディング)
録音(レコーディング)は、音楽制作において“素材を形にする”最も本質的なステップです。ここでは、実際に歌や楽器の演奏を録音していき、曲の骨格を構築していきます。
仮録音を参考にしながらパートごとに録音を進めたり、一発録りでバンド感を出したりと、目的に応じて進め方を選びます。録音は「正確さ」と同時に「表現力」も求められる重要な作業です。
録音で意識したいポイント:
- 仮録音を参考にしながら、順番にパートごとの録音を進める
- 一発録り(全員同時)か、パート録り(個別録音)かを選ぶ
- 納得いくまで何テイクも録ることもある
録音時には、音程やリズムだけでなく、「表現力」も重視されます。
宅録の場合は、自分のペースで何度も録り直せるのがメリット。スタジオ録音では、限られた時間の中で集中力を保つことが求められます。
Step 4:編集・補正(ピッチ補正・パンチイン)
編集・補正は、録音した音源を“聴きやすく整える”ための重要なステップです。
録音直後の音には、音程のズレやリズムのばらつき、ノイズなどが含まれていることが多く、そのままでは違和感を与える可能性があります。
この段階では、ピッチ補正やタイミングの調整、ミス部分の録り直し(パンチイン)などを通じて、楽曲の完成度を高めていきます。一見地味に思える作業ですが、作品全体の質を左右する裏方の主役ともいえる重要な工程です。ピッチ補正(音程を自然に調整)やタイミングの修正、ミス部分の撮り直し(パンチイン)などを通じて、楽曲としての完成度を高めていきます。
整える作業は地味に見えて、作品全体の質を左右する”裏方の主役”とも言える工程です。
- パンチイン(ミスや気に入らない部分だけを撮り直し、別のテイクで上書きする)
- ノイズ除去や余分な音のカットなどの整音作業
編集では、聞いていて違和感のない仕上がりに整えることが重要です。
プロの現場でも補正は一般的に行われており、「整えて完成形に近づける」のがこの工程の役割です。
宅録では、DAW(音楽編集ソフト)を使って自分で行う人も多く、編集スキルが求められる場面でもあります。
Step 5:マスタリング(最終仕上げ)
マスタリングは、音源を“作品として仕上げる”最終工程です。いくら演奏や編集の質が高くても、音量やバランスが整っていないと、聴き手にとって聴きづらい仕上がりになってしまいます。
ここではまず、各パートの音量・定位・音質などを調整する「ミキシング」を行い、その後、全体の音圧や質感を整える「マスタリング」へと進みます。
この工程を通して、楽曲は“音源”として完成し、配信やCD化に対応できるクオリティになります。
- ミキシング:各パートの音量・定位・音質などを調整して、楽曲としてのバランスを整える
- マスタリング:完成した楽曲全体の音圧や音質を整え、配信やCD化に適した状態に仕上げる
ミックス次第で楽曲の印象は大きく変わるため、エンジニアの腕が問われる場面でもあります。宅録でもプラグインや自動マスタリングツールを使えば、ある程度自力で完結させることも可能です。
レコーディングに必要な機材と準備
.png?w=360&fm=webp&q=70)
レコーディングのクオリティは、どれだけ事前にしっかり準備できるかで大きく変わります。ここでは、スタジオ録音・自宅録音(宅録)それぞれに必要な持ち物や機材、そして録音当日の体調管理まで、失敗しない準備のポイントをまとめます。
スタジオに持っていくべきもの
スタジオには多くの機材が揃っていますが、自分で準備すべきものも意外と多いです。忘れ物をするとスムーズに進まないだけでなく、録音のクオリティにも影響が出ることもあります。
【主な持ち物チェックリスト】
- 自分の楽器・シールド
ギター・ベース・エフェクターなど。接続用のケーブルも忘れずに持参しましょう。
- 歌詞カード
スマートフォンだけでなく、紙の歌詞カードがあると安心です。
- 飲み物
ボーカルの場合は、喉のケアのために持っておくと良いでしょう。
- メトロノームのテンポ指示や参考音源
セッティング時に役に立つので、事前に準備しておくとスムーズです。
- スマホの充電器・筆記用具
メモや連絡用に、意外と活躍します。
録音当日はバタバタしがちなので、事前にリストを作ってチェックしておくのが安心です。特に、初めてスタジオを使う人は、事前にスタッフに「何を持って行けばいいか」確認しておくのもおすすめです。
自宅で録音する場合の必要機材
宅録(自宅録音)に挑戦するなら、必要な機材を揃えて環境を整えることが第一歩です。最近は手頃な価格の宅録セットも多く、初心者でもすぐにスタートできます。
宅録に必要な基本機材
- パソコン(PC):録音や編集を行うDAWソフトを動かすための中心機器。作業のベースになります。
- DAWソフト(音楽制作アプリ):音を録音・編集・加工するためのアプリ。Studio One や GarageBand などが代表的です。
- オーディオインターフェース:マイクや楽器の音をパソコンに取り込むための装置。音質にも大きく関わります。
- マイク:声や音をクリアに録音するために欠かせない機材。ボーカルにはコンデンサーマイクがおすすめです。
- ヘッドホン:録音中の音を正確にモニターするために必要。密閉型が一般的です。
これらを揃えることで、自宅でも本格的な録音ができるようになります。最近は初心者向けの機材セットもあり、3〜5万円台からスタート可能です。
宅録にはさまざまな機材が必要ですが、詳しくは別記事で解説していますので、気になる方はチェックしてみてください。
体調・服装・食べ物などの当日準備
レコーディングは技術だけでなく、体調や集中力の管理も成果に直結します。
とくにボーカル録音では、わずかな体調の変化が声の質に大きく影響するため、以下のような準備が大切です。
当日の体調管理・身支度のポイント
- 喉にやさしい飲み物を用意する
常温の水やハーブティーがおすすめです。ミルク・炭酸・冷たい飲み物は避けましょう。
- リップクリームや喉スプレーでケア
口の乾燥を防ぎ、録音中のノイズ対策にもつながります。
- 服装はシンプルで静かな素材を選ぶ
衣擦れやアクセサリーの音が入らないように気をつけましょう。
- 食事は録音の1時間前までに軽めに済ませる
胃が重いと声が出にくくなることがあるため、消化の良い食事がおすすめです。
- 録音直前のスマホやSNSの通知をオフにしておく
録音前は集中できる環境を整えておくことも大切です。
レコーディングにかかる費用と料金相場
レコーディングには、スタジオ代やエンジニア費用、機材など、さまざまなコストがかかります。ここでは、スタジオ録音と宅録の費用の目安や、1曲あたりの録音に必要な時間と予算について、初心者にもわかりやすく解説します。
スタジオ録音の料金例
スタジオ録音にかかる費用は、場所や設備のグレードによって大きく変わります。
以下は、一般的なスタジオ利用時の費用目安です。
- スタジオ利用料:1時間あたり約 3,000円〜10,000円
地方の個人スタジオでは比較的安く、都市部の有名スタジオでは高額になる傾向があります。 - レコーディングエンジニアの人件費: 1日(8時間)で 15,000円〜50,000円程度
エンジニアが録音・編集・音質調整を担当してくれます。料金にはスキル差が反映されることが多いです。 - 機材レンタル費(オプション):
マイクやアンプ、ドラムセットなど、スタジオにない機材を借りると追加で数千円〜かかる場合も。
スタジオ録音は「音質」「サポート」「信頼性」が高い反面、1日で数万円単位の出費になることを前提にスケジュールや予算を組む必要があります。
自宅録音とのコスト比較
一方、宅録は初期費用はかかるものの、長期的にはコスパの良い選択肢です。
初期費用の例(必要機材の合計金額目安)
- PC(またはMacbook):100,000円~
- オーディオインターフェース:10,000円~30,000円
- マイク:10,000円~50,000円
- DAWソフト:0円~30,000円(Studio One / Logic / Ableton Liveなど)
{DAWの費用}
無料のものもありますが、より本格的な機能を使うには月額プランや買い切りが必要な場合もあります。
1曲あたりの録音時間と予算
「1曲レコーディングするのに、どれくらいの時間と費用がかかるの?」という疑問を持つ方は多いでしょう。
ここでは、1曲あたりの録音にかかる時間と料金相場について、初心者向けにわかりやすく解説します。
レコーディングにかかる時間の目安
- 1曲のレコーディング時間は、平均5〜10時間程度が一般的です。
これは楽器やボーカルの録音、テイク選び、休憩時間なども含めた合計時間です。
※特に初めてのスタジオ録音では、思ったよりも時間がかかることが多いため、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。
レコーディング費用の相場(スタジオ録音の場合)
- スタジオ代:1時間あたり 3,000〜10,000円
- エンジニア費用:1日(約8時間)で 15,000〜50,000円前後
- 機材レンタル代:必要に応じて加算される場合あり
これらをすべて含めると、1曲あたりの総費用は約30,000〜100,000円程度が目安です。
※編集(ピッチ補正など)やミックス・マスタリングの料金は別途かかるケースが多いため、事前に確認しておきましょう。
宅録との費用比較
レコーディングの方法によって、必要な費用や準備は大きく異なります。
宅録とスタジオ録音、それぞれのコストや特徴を比較して、自分に合った録音スタイルを見つけましょう。
宅録とスタジオの費用比較
項目 | 宅録(自宅録音) | スタジオ録音 |
|---|---|---|
初期費用 | 必要(機材・ソフト購入) | 不要または少額(楽器やデータのみ) |
ランニングコスト | ほぼゼロ(電気代程度) | 毎回スタジオ利用料が発生 |
機材の自由度 | 高い(自分で選べる) | 限定的(スタジオ常設機材) |
録音環境 | 防音やノイズ対策が必要 | プロ仕様の防音・音響環境 |
総合コスト | 長期的にはコスパ良 | 回数が多いと費用がかさむ |
宅録に必要な主な機材・ソフト
分類 | 内容・例 |
|---|---|
マイク | コンデンサーマイク(例:Audio-Technica AT2020 など) |
オーディオインターフェース | マイクとPCを接続(例:Focusrite Scarlett など) |
DAWソフト | 録音・編集ソフト ・買い切り:Logic Pro、Studio One など ・月額型:Ableton Live(サブスクプランあり) |
ヘッドホン | モニターヘッドホン(例:Yamaha HPH-MT5、SONY MDRシリーズなど) |
その他 | ポップガード、マイクスタンド、ケーブルなど |
宅録とスタジオ録音のどちらが良いかは、目的や予算、求めるクオリティによって選びましょう。初心者の方は、まず宅録で試してみるのもおすすめです。
まとめ|あなたの音楽を“作品”にする第一歩
.png?w=360&fm=webp&q=70)
レコーディングは、「演奏」や「歌」を“作品”として形にするための大切なプロセスです。
初めての方にとっては、機材の準備や費用、録音の流れなど不安に感じる点も多いかもしれません。ですが、少しずつ知識を身につけ、自分なりのスタイルを見つけていくことで、レコーディングはぐっと身近なものになります。
特に最近は、宅録(自宅レコーディング)という選択肢も広がり、プロに頼らずともクオリティの高い音源制作が可能になっています。
自分の音楽をより多くの人に届けたいなら、まずは「録ってみること」から始めてみるのが一番の近道です。
不安があっても準備次第で楽しめる
初めてのレコーディングは、「うまく録れるかな?」「機材の使い方が不安…」と、緊張や戸惑いを感じるかもしれません。
ですが、事前の準備や流れの理解ができていれば、録音はもっと楽しく、前向きな体験になります。
録音前に曲の構成を整理したり、仮録音(プリプロ)で流れを確認したりすることで、本番もスムーズに。スタジオでの録音でも、宅録でも、準備をしっかり行うことで、「やってみてよかった」と思えるレコーディングになります。
宅録でもスタジオでも、まず一歩踏み出そう
レコーディングには「宅録(自宅録音)」という気軽な選択肢もあれば、プロ仕様のスタジオ録音という本格的な方法もあります。どちらにもメリットがあり、自分の環境や目的に応じて選ぶことができます。
たとえ最初はうまくいかなくても、録音を繰り返すことで音楽表現の幅や完成度は、どんどん広がっていきます。完璧を目指しすぎず、まずは「1曲録ってみる」こと。それが音楽制作の大きな第一歩です。音楽が音源として形になったとき、それはもう立派な作品です。宅録からでも、スタジオからでも、レコーディングという体験が、次の表現へとつながっていきます。
あなたの音楽を誰かに届けたい -そう思ったその気持ちこそが、音楽活動の本当のスタートラインです。
このページが、あなたの「初めてのレコーディング」の参考になれば幸いです。