「自分で曲を作ってみたいけど、コード進行ってどうやって作ればいいの?」
そんな悩みを持つ初心者の方に向けて、この記事ではコード進行の仕組みから作り方、そしてジャンル別のおすすめ進行までをわかりやすく紹介します。
ギター1本やピアノだけでも、コード進行の基本を押さえればオリジナル曲を作ることは十分可能です。
音楽理論が難しく感じる人でも大丈夫です。
この記事を読み終えるころには、「なんとなく曲の流れがわかってきた」「自分でもコード進行を作れそう!」と思えるはずです。
まずは基本!コードとは?
.png?w=360&fm=webp&q=70)
コードの意味と役割
まず「コード(Chord)」とは、複数の音を同時に鳴らして作る“和音”のことを指します。
たとえばピアノで「ド・ミ・ソ」を同時に弾くと、それが「Cコード(Cメジャー)」です。
この「複数の音を同時に鳴らす」という考え方がコードの基礎となります。
メロディー(歌のライン)は一本の“線”ですが、コードはそれを支える“背景の色”のようなものです。
同じメロディでも、どんなコードをつけるかで雰囲気がまったく変わります。
たとえば、明るいコードをつければ前向きでポップな印象に、マイナーなコードをつければ、切なく感情的な印象になります。
つまりコードは、曲の感情を操る「スイッチ」のような存在です。
映画でいえばBGMのように、聴き手の気持ちを自然と誘導してくれる大切な要素なのです。
コードの構成音(3和音=トライアド)を理解しよう
基本的なコードは3つの音で構成されています。
これを「トライアド(Triad)」=“3つの音”という意味で呼びます。
たとえば「Cメジャー」の場合:
- C(ド)=ルート(根音)
- E(ミ)=3度音(明るさ・暗さを決める音)
- G(ソ)=5度音(安定感を与える音)
この3音のバランスがコードのキャラクターを決めています。
ルート(Root)
この音は、コードの“土台”となる音になります。
曲の中で「どの高さを中心に響かせたいか」を決める、まさに家の基礎のような存在です。
Cコードなら「C」、Amなら「A」がルートになります。
今後既存の曲のコードを耳コピする際に、このルート音は非常に役立ちます。
3度音(Third)
この音は、明るいか暗いかを決定づける、コードの“性格”を作る音になります。
長3度(メジャー)なら明るくポジティブ、短3度(マイナー)なら暗くエモーショナルな響きになります。
このわずか半音の違いが、曲の印象を180度変えます。
5度音(Fifth)
この音は、コードの安定感を生み出す支えのような存在です。
ルートと5度は完全5度の関係で、どんな音楽でも最も調和しやすい音程です。
5度を抜いてもコードは成り立ちますが、入れることで響きが豊かになります。
ルート音とルート音の5度の音のみで構成されているコードをパワーコードと呼びます。
このコードは明暗の響きがないため力強いサウンドを持っており、ロックに多用されます。
メジャーコードとマイナーコードの違い
コードには大きく分けて「メジャー」と「マイナー」の2種類があります。
これは3つの音の“間隔”(音程)の違いで決まります。
- メジャーコード:明るく、前向きな響き(Key=C majorの場合:C、G、F)
→ コードが「C」の場合、構成される音はド・ミ・ソ(C・E・G)になります。一番低い音(ド)はルート音と呼び、コードを下から支える役割を持ちます。
ルート音から鍵盤(白鍵と黒鍵)で4つ上の音を長3度と呼び、メジャーコードの真ん中の音に当たります。このルート音と長3度との間隔が「明るい」響きを生みます。 - マイナーコード:少し切なく、落ち着いた響き(Key=C majorの場合:Am、Em、Dm)
→ コードが「Am」の場合、構成される音はラ・ド・ミ(A・C・E)となります。
ルート音(ラ)から鍵盤で3つ上の音を短3度と呼び、マイナーコードの真ん中の音に当たります。
ほんの半音違うだけで、しっとりした「暗い」響きに変わります。
たとえば「Cメジャー(C・E・G)」と「Aマイナー(A・C・E)」は、実はCとEを共有しているのに、まったく違う雰囲気になります。
この違いを耳で聴き比べるのがおすすめです。
ピアノやギターでC→Amと弾くだけで、メジャーコードとマイナーコードの響きの違いを体感できるはずです。
この明るい/暗いの違いを感覚で覚えることが、作曲の第一歩です。
そもそもコード進行とは?
.png?w=360&fm=webp&q=70)
コード進行とは?
「コード進行(Chord Progression)」とは、
複数のコードを一定の順番で並べて、音楽に流れを作ることです。
たとえば、C(ドミソ)だけをずっと鳴らしていても、曲に変化が生まれず、平坦な面白みのない印象を与えます。
しかし、「C → G → Am → F」といった具合に、コードを変化させていくことによって、
曲に展開が生まれます。これがコード進行の役割です。
実際、ほとんどのポップス・ロック・R&Bなどの現代音楽は、
この“コードの流れ”によって感情の起伏や物語性を作っています。
コード進行を理解することで、曲をどのような展開にしたいのか、どのようなストーリーに仕上げたいかを意識的にコントロールできるようになります。
たとえば、
- 明るく前向きにしたい → メジャー中心の進行
- 切なくしたい → マイナー進行
- ドラマチックにしたい → 転調やドミナントを強調
というように、感情の設計図を自分で描けるようになるのです。
つまりコード進行は、「音楽のストーリーライン」であり、曲の印象づける重要な要素です。
コード進行の基本構造(トニック・サブドミナント・ドミナント)
コード進行を理解する上で、ダイアトニック・コードはとても重要です。
ダイアトニック・コードとは、1つのキー(調)に含まれる7つの基本コードのことを指します。
さらに、ダイアトニック・コードの中でトニック、サブドミナント、ドミナントの3つの役割に分類できます。
この3つの役割を理解すると、コード進行について理解しやすくなり、耳コピだけでなく、自分で心地の良いコード進行を作ることができます。
役割 | 感覚 | 代表コード(Cキーの場合) |
トニック(T) | 安定・落ち着き・“帰る場所” | C(I)、Em(Ⅲm) |
サブドミナント(S) | 少し動きが出る・広がりを感じる | Dm(Ⅱ)、F(IV) |
ドミナント(D) | 不安定・緊張感・“次に行きたい” | G(V)、 |
トニック(T)
トニック(T)はダイアトニック・コードの中で、最も安定感のある響きを持っています。
「家」に例えるとリビングのような場所で、聴いていて落ち着く響きを持ちます。
CメジャーキーならC、Em、Amがその役割に当たります。
曲の始まりや終わりでCが鳴ると、「あ、帰ってきた」と感じるのはこのためです。
サブドミナント(S)
サブドミナント(S)は少し不安定な響きを持っており、コード進行に変化をもたらす役割を持っています。つまり、コード進行において穏やな変化を感じさせるコードです。
CキーならDm、Fがその役割に当たります。
例えば、C→Fと進むと、少し広がるような安心感が生まれます。コード進行を作る際はトニックを最初にして、次のコードにサブドミナントにすると、綺麗なコード進行になります。
ドミナント(D)
ドミナント(D)は、コード進行に緊張感と推進力を与える重要な役割を持っています。
CキーならG、Bm7♭5に当たります。実際に、Gを鳴らすと自然と「Cに戻りたい」と感じると思います。。
この“戻りたい力”を「ドミナントモーション」と呼びます。
基本的なコード進行
このトニック・サブドミナント・ドミナントの3つで構成されるコード進行の基本的な形は、「T → S → D → T」です。
Key=C majorの場合、C → F → G → Cという進行だけでも綺麗な曲の流れに仕上がります。
有名なコード進行を例に挙げると
- 「C → G → Am → F」(王道進行)
- 「Am → F → C → G」(感傷的でエモい進行)
- 「C → Em → F → G」(爽やかで前向きな進行)
「C → Em → F → G」は「T → T → S→ D」になっていますが、どのコード進行も「T → S → D 」という流れが共通しています。
この「T(安定) → S(展開)→ D(緊張) → T(解決)」のコード進行が現代音楽のコード進行の基礎となっています。
初心者でもできるコード進行の作り方ステップ
.png?w=360&fm=webp&q=70)
① Key(調)を決める
まずは曲のKeyを決めましょう。
初心者なら、C majorがおすすめです。このKeyは発見のみで構成されており、非常に覚えやすいです。
C majorとA minorは構成されている音が同じであるため、ここでは「明るい曲ならCメジャー」「切ない曲ならAマイナー」くらいの感覚でOKです。
② よく使われる進行を参考にする
最初は“王道”から学ぶのが一番の近道です。
定番の進行を使うだけで、自然と完成度の高い曲になります。
- I–V–vi–IV(C–G–Am–F)=王道進行
- I–vi–IV–V(C–Am–F–G)=50’s進行
これらは日本のポップスでも多用されており、弾くだけで「聴いたことある!」と感じるでしょう。
③ 好きな曲のコードを参考にしてみる:できれば、耳コピをしてみる
好きなアーティストの曲を聴いて、「この流れ好き!」と思ったら、ぜひその曲のコード進行を参考にしてみましょう。
最初は無理に耳コピをせず、Googleなどのサイトで調べてみましょう。
コード進行を実際に弾いたり、使っていくことによって少しずつ耳がコード進行を認識するようになります。
耳コピの方法
- ベースの音=ルート音を聴きとる
- ルート音に沿って、ダイアトニック・コードを弾いてみる。
- 実際に調べてみる
もし、耳コピをする場合はルート音とダイアトニックコードが重要になります。
手順としては、一番低いベースの音=ルート音を聴きます。
基本的にルート音とそのコードは同じ音になります。
例えばCの場合、基本的にベースの音はCになっていることが多いです。
次にルート音を聞き取れたら、ダイアトニック・コードで当てはめていきます。
これにより、スムーズかつ簡単にコード進行を耳コピすることができます。
この方法で聞き取れなかった場合、無理せず調べてみましょう。
その後、そのコードを実際に弾いてそのコードが持つ響きを感じましょう。
これの流れを繰り返すことによって、絶対音感を持ち合わせていなくても耳コピできるようになります!
耳コピおすすめツール
● Moises

これはAIが音源を分離し、ボーカルやコード、ベースラインを自動で抽出してくれるツールです。
好きな曲のコード進行をリアルタイムで確認できるので、耳コピの練習に最適です。
スマホアプリ版もあり、初心者でも簡単に使えます。また、無料版では月に最大5曲まで分析してくれます。
● Hookpad
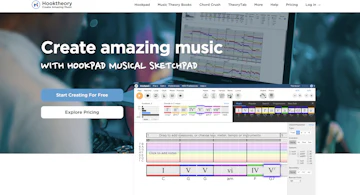
これは、クリック操作だけでコード進行を自動生成してくれる作曲支援ツールです。
コードを変えるとリアルタイムでメロディも変化するので、感覚的に学べるのが魅力です。
ジャンル別おすすめコード進行集
.png?w=360&fm=webp&q=70)
■ ポップス系(明るくキャッチー)
進行例:C–G–Am–F(王道進行)
ポップス系の曲でおすすめのコード進行は、「王道進行(Ⅰ–Ⅴ–Ⅵm–Ⅳ)」です。
J-POPをはじめ、世界中のポップスで最も多く使われている黄金パターンです。
明るく前向きで、耳なじみが良く、初心者でも心地よく聴くことができます。
- 嵐 - Happiness
- back number - 高嶺の花子さん
- One Direction - Story of My Life
このコード進行の特徴は、Aメロ・Bメロ・サビのすべてで使っても不自然にならず、曲の基盤として使いやすい点です。そのため、とりあえず困ったらこのコード進行を使うといいでしょう。
応用として、AmをFに変えてみたり、最後のFをDmにするだけでも少し切ない印象に変わります。
■ バラード系(切ない・儚い)
進行例:Am–F–C–G(カノン進行)
この「カノン進行(Ⅵ–Ⅳ–Ⅰ–Ⅴ)」は、感情をじわっと引き出す王道の“泣けるコード進行”です。
ピアノバラードや失恋ソングにぴったりで、静かな導入からクライマックスまで幅広く使えます。
- 平井堅 - 瞳をとじて
- 宇多田ヒカル - First Love
- Ed Sheeran - Perfect
このコード進行を使う際は、テンポをゆっくりにして、アルペジオで優しく弾くとよりエモーショナルに仕上がります。
また、感情を“溜めて放つ”構造を持つため、歌詞のメッセージを強調したい曲に最適です。
応用として、最後のGをE7に変えると、次の展開につながる期待感を作れます。
■ R&B / Lo-fi系(おしゃれ・浮遊感)
進行例:Dm7–G7–Cmaj7(Ⅱm7–Ⅴ7–Ⅰmaj7)
おしゃれなサウンドを持つコード進行は「ツーファイブワン進行(Ⅱ- Ⅴ-Ⅰ)」です。
ジャズやソウル、R&Bで頻繁に使われるコード進行で、テンションコードを含むため非常に洗練された印象になります。
柔らかく包み込むような“浮遊感”を出したいときにおすすめです。
- Bruno Mars - Versace on the Floor
- Lauv - I Like Me Better
このコード進行はエレピやジャズギターの音色と相性抜群であり、裏拍に軽くスウィング感を入れると一気にR&Bらしいおしゃれさを演出できます。
また、「夜の空気」「チルアウト」「シティ感」を作りたいときにおすすめの進行です。
応用として、Cmaj7をAm7に変えると、少し哀愁を帯びたLo-fi感を演出することができます。
■ ロック / アイドル系(力強く爽快)
進行例:C–Bb–F(Ⅰ–♭Ⅶ–Ⅳ進行)
このコード進行は、エネルギッシュで疾走感のある進行です。
ロックやアイドルソングによく見られる「モーダル進行(Mixolydian風)」で、
開放感と勢いを両立できます。
このコード進行を使う際は、「前に突き進む」「青春感」「ライブ映え」という印象を与えるため、ギターのパワーコードで鳴らすと非常に映えます。
- ONE OK ROCK - The Beginning
- Official髭男dism - 宿命
このコード進行を使う際は、Bb(♭Ⅶ)を強調することで“非日常感”を演出することができます。また、このコード進行をサビで使うと一気に盛り上がります。
応用として、最後にG(Ⅴ)を加えると、よりメジャー感のある展開にも変化できます。
コード進行を自分らしくアレンジするコツ
1. テンションコードを加える(7th, 9thなど)
基本の3和音に1音足すだけで、一気に大人っぽく、おしゃれな響きになります。
例えば、C → Cmaj7 → C7 のように変化させると、コード進行に更なる深みを与えます。
コツとしては、 テンションは多用しすぎず、1〜2か所でアクセントとして使うとより効果的になります。
- maj7(メジャーセブンス)…穏やかで都会的
- 7(セブンス)…ブルージーで前に進みたくなる感覚
- 9(ナインス)…浮遊感・幻想的な雰囲気
2. 転調を使って展開を作る
同じ進行が続くとマンネリしやすいですが、サビで半音または全音上げるだけで劇的な変化を生み出せます。このようにサビでKey(調)が変化する「サビ転調」は、感情のピークを作る定番の使い方になります。。
- King Gnu - 白日
- Official髭男dism - Pretender
転調前の最後のコードに共通音を持つコード(例:G7 → A♭)を挟むと、スムーズに転換できます。また、終盤で使うことにより、物語のクライマックスを演出することができます。
3. リズムやアルペジオで個性を出す
コード進行そのものは同じでも、リズム・奏法・音色を変えるだけで印象はまったく別物になります。 DAWでドラムパターンを変えたり、コードを打ち込みにすることで分散させるだけでも世界観が一変します。
- ストロークを軽くして“アコースティック感”を出す
- アルペジオで優しく弾き、繊細な空気感を作る
- シンコペーションや16ビートでリズムを“ずらす”
まとめ|理論より“耳で感じる”ことが上達の近道

コード進行の理論を学ぶことは大切ですが、最も重要なのは「自分の耳で心地よい」と感じる感覚です。
理論に縛られすぎず、Moisesなどのツールを使って好きな曲を分析したり、実際に弾いて“自分が心地よいと感じる進行”を探してみましょう。
そうして少しずつ「自分の中の音感」が育っていけば、あなたらしいオリジナルサウンドが必ず見つかります。
今日から、あなたの“はじめての作曲”をスタートさせましょう!

.png&w=1200&q=75&dpl=dpl_Gti1yAtuhDNdb8sAi6p7jDFTsNLj)











